子どもの教育について考える際、多くの親が直面する重要な選択が「中学受験」と「高校受験」のどちらを選ぶかという問題です。首都圏では小学6年生の約5人に1人が中学受験に挑戦している現状がありますが、果たしてどちらの道を選ぶのが正解なのでしょうか。
本記事では、実際の経験者の声や客観的なデータを基に、中学受験と高校受験の難易度や費用対効果を徹底比較し、あなたの家庭に最適な選択肢を見つけるためのヒントをお伝えします。
中学受験と高校受験はどちらが大変?基本的な違いを理解しよう

中学受験と高校受験どっちが難しい?偏差値と競争環境の違い
偏差値の見方が全く異なる理由
中学受験と高校受験では、同じ偏差値でも実際の難易度が大きく異なります。これは受験する母集団の違いによるものです。
中学受験では受験勉強に力を入れている学生だけで母集団が形成されているため、偏差値が低く出ます。一方、高校受験は中学3年生の大多数が受験するため、母集団の学力に差が生じて偏差値が高くなるのが特徴です。一般的に中学受験と高校受験では、偏差値に10以上の差があるといわれています。
具体的には、中学受験で偏差値45の学校は、高校受験では偏差値55~60程度に相当すると考えられています。つまり、中学受験の偏差値45でも、実際には相当なレベルの学校だということです。
入試問題の難易度比較
中学受験の入試では応用問題など教科書の範囲を超えて出題されていることが多く、学校の授業だけでは自力で解決することが難しく、中でも算数は中学生に出題しても解けないような難易度が高い問題もあります。
対して高校受験では、基本的に中学校で習う範囲から出題されることが一般的で、塾に通っていない子どもでも自身に見合った高校であれば受験をクリアできることもあります。
首都圏模試センターによる最新データ
首都圏模試センターが行った調査によると、2023年度の首都圏の中学受験者数は、私立中学と国立中学を合わせて5万2,600人とされています。中学受験者数の1回目のピークである1991年の5万1,000人と、2回目のピークとなる2007年の5万500人を上回り、史上最多の人数となりました。
| 項目 | 中学受験 | 高校受験 |
|---|---|---|
| 偏差値の見方 | 同偏差値でも実質10~15高い | 中学受験より10~15低く表示 |
| 受験者層 | 学習意欲の高い層のみ | 中学3年生の大多数 |
| 入試問題 | 教科書範囲を超えた応用問題 | 中学校で習う範囲が基本 |
| 準備開始時期 | 小学3~4年生から | 中学1~3年生から |
| 競争の激しさ | 非常に激しい | 中学受験より緩やか |
| 親のサポート度 | 必須(親主導) | 子ども主体で進められる |
この数字から分かるように、中学受験への注目度は年々高まっており、競争も激化していることが伺えます。
中学受験 高校受験 コスパで比較!総費用と時間的負担
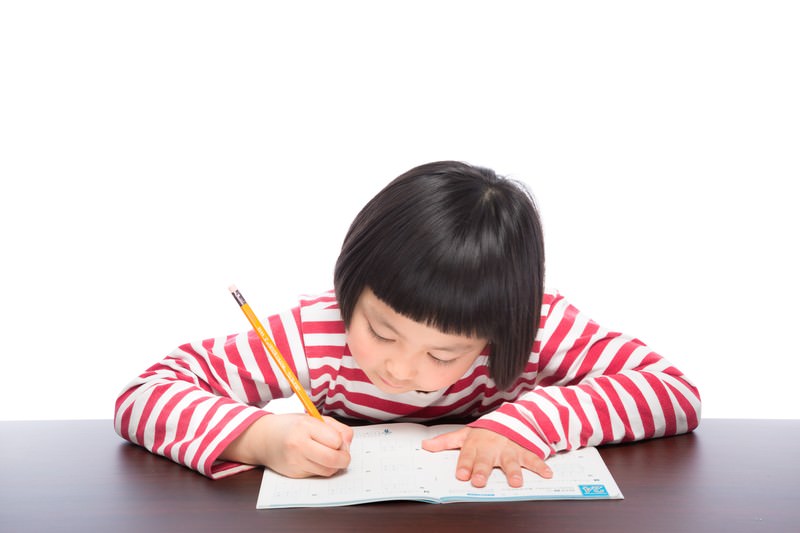
塾費用の実態調査結果
文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、中学受験と高校受験にかかる塾費用には大きな差があることが判明しています。
- 小学4年生:年間約70万円
- 小学5年生:年間約90万円
- 小学6年生:年間約120万円
- 3年間合計:約280~300万円
- 中学1年生:年間約27万円
- 中学2年生:年間約29万円
- 中学3年生:年間約46万円
- 3年間合計:約100万円
| 項目 | 中学受験ルート | 高校受験ルート |
|---|---|---|
| 塾費用(3年間) | 約300万円 | 約100万円 |
| 学費(中高6年間) | 私立:約600万円 | 公立中+公立高:約150万円 |
| 総費用 | 約900万円 | 約250万円 |
| 費用差 | – | 約650万円安い |
時間的負担の比較
中学受験の時間的負担は深刻で、小学6年生では週5日、1日4~5時間の勉強が当たり前となっています。これは年間約1,000時間に相当し、小学生の貴重な時間の大部分を受験勉強に費やすことになります。
高校受験では、部活動との両立も可能で、本格的な受験勉強は中学3年生からでも間に合うケースが多く、時間的な余裕があります。
私立中高学費の現実
文部科学省の2023年度調査によると、私立中学の授業料など学習費総額は3年間で467万円でした。2012年度では388万円だったのが約80万円増加しており、物価上昇に伴って学習費も値上がりしています。
公立中学校であれば150~160万円程度で済むことを考えると、私立中学校は公立中学校の約3倍の費用がかかることになります。
出典:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
中学受験したら高校受験しなくていい?メリットとデメリット

中学受験に成功して中高一貫校に進学した場合、確実に高校受験を回避できるという大きなメリットがあります。これにより以下のような恩恵を受けることができます。
1. 高校受験のストレスがない 中高一貫校では基本的に内部進学が可能なため、高校受験という大きなハードルを回避できます。これにより中学3年生の時期を受験勉強ではなく、部活動や趣味、将来に向けた準備に充てることができます。
2. 6年間一貫したカリキュラム 多くの中高一貫校では、中学1年生から高校3年生までの6年間を見据えたカリキュラムが組まれています。特に数学や英語では、高校内容を中学のうちに先取り学習することで、大学受験により多くの時間を割くことが可能になります。
3. 安定した人間関係 6年間同じメンバーで過ごすことで、深い友人関係を築くことができ、安定した学校生活を送ることができます。
一方で、中高一貫校には以下のような課題もあります。
1. 中だるみのリスク 高校受験がないことで、中学2~3年生の時期に学習意欲が低下する「中だるみ」現象が起こりやすくなります。実際に、中学受験成功後に学習意欲が急降下するケースは珍しくありません。
2. 環境の固定化 6年間同じ環境で過ごすため、多様な価値観に触れる機会が限定される可能性があります。公立中学校のような多様性のある環境での経験が不足する場合があります。
3. 費用負担の継続 私立中高一貫校の場合、6年間継続して高い学費を支払う必要があります。途中で家計状況が変化した場合でも、費用負担は継続します。
| 項目 | 中高一貫校 | 高校受験ルート |
|---|---|---|
| 高校受験の有無 | なし | あり |
| 学習進度 | 先取り学習可能 | 標準的な進度 |
| 人間関係 | 6年間固定 | 中学・高校で変化 |
| 多様性 | 限定的 | 豊富 |
| 費用 | 6年間私立学費 | 公立なら大幅削減 |
| 中だるみリスク | 高い | 低い(高校受験があるため) |
実際の保護者の声
ひまわり教育研究センターの調査によると、偏差値60以上の中学校に通う子どもをもつ保護者150人のうち67.3%が「後悔していることがある」と回答しています。主な後悔理由は:
- 成績や宿題のことで叱ったこと(42.4%)
- 遊びをさせすぎたこと(24.8%)
- 勉強をさせすぎたこと(19.8%)
この結果からも、中学受験には一定のリスクが伴うことが分かります。
中学受験vs高校受験、どちらが大変かを徹底比較

世帯年収500万でも可能?中学受験と高校受験の費用比較
年収500万円の家庭にとって、子どもの教育費は家計に大きな影響を与える重要な要素です。手取り年収が約400万円程度となる中で、教育費にどこまで投資できるかを慎重に検討する必要があります。
中学受験を選択した場合の家計負担
世帯年収500万円で中学受験を選択した場合、以下のような費用負担が発生します:
- 年収500万円の家庭の手取り(約400万円)に対して、年間100万円の塾費用
- 家計に占める割合:約25%
- 年間100万円の学費負担
- 家計に占める割合:約25%
つまり、中学受験ルートを選択すると、9年間で家計の25%を教育費に充てることになります。
高校受験を選択した場合の家計負担
一方、高校受験ルートの場合:
- 年間約33万円の塾費用
- 家計に占める割合:約8%
- 年間25万円程度
- 家計に占める割合:約6%
| 項目 | 中学受験ルート | 高校受験ルート | 差額 |
|---|---|---|---|
| 9年間総費用 | 約900万円 | 約250万円 | 650万円 |
| 年収に対する割合 | 約25% | 約7% | 18%軽減 |
| 月額負担 | 約8.3万円 | 約2.3万円 | 6万円軽減 |
年収500万円家庭での中学受験成功事例
実際に年収500万円程度で中学受験に成功している家庭もあります。その場合の工夫点は:
- 早期からの教育費積立:子どもが生まれた時から月2万円程度を教育費として積立
- 祖父母からの援助:入学金や制服代などで一時的な援助を受ける
- 母親の働き方調整:塾の送迎等のため、フルタイムからパートに変更
- 家計の徹底見直し:住宅ローンの借り換え、保険の見直し等で月3~5万円の節約
高校受験ルートの経済的メリットがさらに大きくなる重要な変化が2025年4月から始まります。
2025年度の変更点:
- 公立高校の所得制限完全撤廃:世帯年収に関係なく年額11万8,800円支給
- すべての家庭が対象:年収1,000万円を超える家庭でも支援対象
2026年度予定の変更点:
- 私立高校の支援大幅拡充:年額39万6,000円→45万7,000円に増額
- 私立高校も所得制限撤廃:全国平均授業料相当額まで支援
| 項目 | 中学受験ルート | 高校受験ルート | 差額 |
|---|---|---|---|
| 9年間総費用 | 約900万円 | 約150万円(大幅削減) | 750万円 |
| 年収に対する割合 | 約25% | 約4% | 21%軽減 |
| 月額負担 | 約8.3万円 | 約1.4万円 | 6.9万円軽減 |
東京都では2024年度から所得制限を撤廃し、都立高校・私立高校ともに実質無償化を先行実施しています。この制度により、同じ高校に通うのに住んでいる場所によって家計負担に差が生じる問題も解消されつつあります。
年収500万円家庭では、中学受験は決して不可能ではありませんが、相当な家計管理と節約が必要となります。一方で高校受験ルートを選択すれば、2025年度からの高校無償化制度拡充により教育費負担を大幅に軽減しながら、他の教育投資や生活の質向上に資金を回すことが可能になります。
中学受験 しなければよかったと後悔する理由TOP3
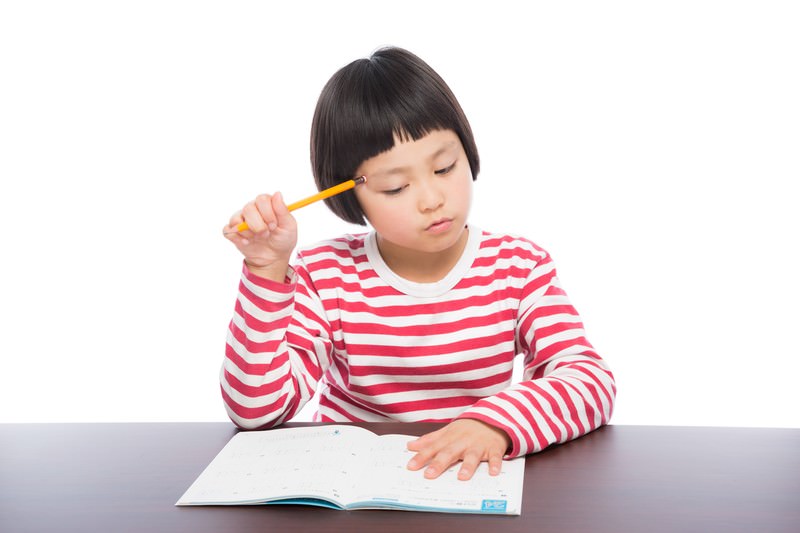
67.3%の保護者が抱える後悔の実態
前述のひまわり教育研究センターの調査では、偏差値60以上の難関中学に合格した家庭でさえ、67.3%の保護者が何らかの後悔を抱えていることが明らかになりました。成功したはずの中学受験で、なぜこれほど多くの家庭が後悔しているのでしょうか。
第1位:成績や宿題のことで叱ったこと(42.4%)
最も多い後悔が「子どもを叱りすぎたこと」です。中学受験では膨大な宿題量と厳しい成績管理が求められるため、親も子どもの勉強に対する意識が高くなり、ついつい口を出してしまいがちです。
実際の体験談: 「毎日夜9時まで塾、帰ってきてからも宿題。できないと私も感情的になって怒鳴ってしまい、息子が泣きながら勉強する姿を見て『こんなはずじゃなかった』と思いました」(小6男子の母親)
第2位:子どもの精神的負担と燃え尽き症候群(19.8%)
中学受験に合格した後、学習意欲が急激に低下する「燃え尽き症候群」に陥る子どもが少なくありません。これは長期間のストレスによる心身の疲労が原因です。
症状の例:
- 自主学習をしなくなる
- 宿題を後回しにする
- 「自分はダメだ」という発言が増える
- 頭痛や腹痛、不眠などの身体的症状
- 友人関係への悩み
実際のケース: 偏差値70の有名大学付属校に合格した男子生徒が、入学後に成績下位グループに甘んじ、「お父さんと、お母さんが行かせたかった学校で、別に僕が行きたかった学校じゃない!中学受験なんて、しなきゃよかった!」と訴えて不登校になったケースも報告されています。
第3位:小学校時代の貴重な体験を奪ったこと(24.8%)
中学受験のため小学校高学年の3年間を勉強漬けにしたことで、以下のような機会を失ったと後悔する親が多くいます:
- 友達との自由な遊び時間
- 家族での旅行や外出
- 習い事(スポーツ、音楽など)への専念
- 読書やゲームなどの趣味の時間
【統計】中学受験後の学習意欲変化
私立中学校に通っている中学生の約7.7%のうち、必ず半数の3.8%が中位以下の成績となり、さらにその半数(1.9%)は下位25%となります。つまり、中学受験に成功しても4人に1人は下位グループに位置することになります。
- 子ども主体の受験にする:親の期待ではなく、子ども自身の意志を尊重
- 適度な息抜きを確保:週1回は完全に勉強から離れる時間を作る
- 結果よりもプロセスを評価:努力そのものを認める声かけを心がける
- 第二志望以下の学校も真剣に検討:「ここでも十分」と思える学校選び
これらの後悔事例を知った上で、自分の家庭にとって本当に中学受験が必要かどうかを慎重に検討することが重要です。
中学受験 やめて高校受験にした家庭の実体験

小学5年生で方向転換した家庭の体験談
東京都大田区在住のAさん(仮名)の事例をご紹介します。長男が小学校低学年の頃から中学受験を目指していましたが、5年生のときに高校受験に切り替えました。
中学受験を始めた理由 実家が医師の家系で、長男は幼いころから「お医者さんになりたい」と口にしていました。「将来の選択肢を狭めないためにも、学習は早めにスタートさせたい」と考え、中学受験を視野に低学年のうちから通塾を開始させました。
転機となった出来事 ところが、その後野球を始めた長男はすっかり夢中になり、「甲子園に行きたい」「野球の選手になりたい」と言い出すように。野球が強くてハイレベルな中学を目指して週4日通塾し、それ以外の時間は野球をするという多忙な毎日が始まりました。
決断の瞬間 学年が上がるにつれ、野球への思いは強まるばかり。次第に受験勉強との両立が苦しくなっていきました。「受験が終わるまで野球を我慢するか、中学受験をやめるか。半年間くらい葛藤がありました」と知香さんは振り返ります。
高校受験コースへの切り替え 悩みを相談した友人から「塾そのものはやめず、高校受験コースに変更してはどうか」という提案を受け、小学5年生の途中で高校受験コースに変更しました。
- 時間的余裕の確保:野球に専念できる時間が大幅に増加
- 子どものストレス軽減:受験プレッシャーから解放され、明るさを取り戻した
- 家族関係の改善:勉強のことで叱る機会が減り、家庭内が平和に
- 費用負担の軽減:中学受験時の年間120万円から年間50万円程度に削減
最終的な進路: 長男は地元の公立中学に進学し、野球部で活躍。中学3年生時には県大会出場を果たし、野球推薦で私立高校に進学しました。
別の家庭の事例:野球と勉強の両立成功ケース
一方で、中学受験を継続しながら野球と両立に成功した家庭もあります。
- 時間管理の徹底:朝4時起床で勉強時間を確保
- 効率的な学習法:苦手分野に集中した学習
- 家族総出のサポート:祖父母も含めた送迎体制
- 明確な目標設定:「野球の強い私立中学」という具体的な目標
| 項目 | 中学受験継続家庭 | 高校受験切り替え家庭 |
|---|---|---|
| 時間的余裕 | 限定的 | 大幅に確保 |
| 子どものストレス | 高い | 軽減 |
| 家族関係 | 緊張状態継続 | 改善 |
| 費用負担 | 年間120万円継続 | 年間50万円に軽減 |
| 最終進路 | 私立中高一貫校 | 公立中→私立高校 |
| 部活動への専念度 | 制限あり | 十分に専念可能 |
- 子どもが明確に他の目標を持った時
- 勉強と他の活動の両立が困難になった時
- 家族関係に深刻な影響が出始めた時
- 経済的負担が家計を圧迫し始めた時
重要なのは、「これまでの投資を無駄にしたくない」という気持ちにとらわれず、子どもの最善の利益を考えて決断することです。
文部科学省の調査によると、以下のような実績が報告されています:
| 大学 | 公立中学出身者の割合 | 私立中学出身者の割合 |
|---|---|---|
| 東京大学 | 約40% | 約60% |
| 早稲田大学 | 約65% | 約35% |
| 慶應義塾大学 | 約55% | 約45% |
| GMARCH | 約70% | 約30% |
この数字から分かるように、公立中学出身者でも十分に難関大学への道は開かれています。
まとめ:中学受験と高校受験どちらが大変かは家庭の状況次第

客観的データから見る結論
本記事で検証してきた様々なデータと実例から、「中学受験と高校受験のどちらが大変か」という問いに対する答えは、家庭の状況や価値観によって大きく異なるということが明らかになりました。
| 評価項目 | 中学受験 | 高校受験 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 学習負担度 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 中学受験の方が圧倒的に高負荷 |
| 費用負担 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | 約650万円の差 |
| 親のサポート度 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | 中学受験は親主導が必須 |
| 子どもの自主性 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | 高校受験の方が子ども主体 |
| 将来の選択肢 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | どちらも難関大学への道はある |
| 精神的負担 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 中学受験の方がストレス大 |
以下の条件が複数当てはまる場合は、中学受験を検討する価値があります:
- 世帯年収700万円以上で教育費に年間100万円以上投資可能
- 子ども自身が明確に私立中学を希望している
- 地元公立中学の環境に不安がある
- 親が中学受験経験者で適切なサポートが可能
- 6年間の継続的な費用負担に問題がない
- 子どもが学習意欲旺盛で競争環境を好む
以下の条件が当てはまる場合は、高校受験ルートがおすすめです:
- 世帯年収500万円前後で教育費を抑えたい
- 子どもに多様な経験をさせたい
- 小学生時代は伸び伸びと過ごさせたい
- 部活動や習い事に力を入れたい
- 地元公立中学の環境が良好
- 子どもが自立心旺盛で自分で目標設定できる
経済的観点からの推奨
特に年収500万円前後の働く大人の皆さんにとって、高校受験ルートは非常にコストパフォーマンスが優秀です:
- 総費用約250万円(中学受験の約900万円と比較)
- 浮いた650万円を大学費用や老後資金に回せる
- 家計圧迫のリスクを大幅に軽減
- 多様な教育投資が可能
中学受験と高校受験の選択で最も重要なのは、以下の3つの要素です:
- 家計の持続可能性:無理のない教育投資かどうか
- 子どもの意思と適性:本人が望む道かどうか
- 家族全体の幸福度:受験によって家族関係が悪化しないか
行動指針
この記事を読んで迷っている方は、以下のステップで検討してみてください:
- 家計シミュレーション:9年間の教育費負担を具体的に計算
- 子どもとの対話:本人の希望と適性を確認
- 地域情報の収集:公立中学校の実情を調査
- 体験授業参加:塾の雰囲気を実際に確認
- 家族会議:全員が納得できる決断を
どちらのルートを選んでも、継続的な努力と適切なサポートがあれば、子どもは必ず成長します。大切なのは、外部の情報に惑わされず、自分の家庭にとって最適な選択をすることです。
出典・参考資料
